

伝統と革新を融合した食文化の教育モデルが始動!
食文化デザインコース新プログラムのご紹介
私たちの食を巡る環境は、ただ今、大きな変革の波に直面しています。物価の高騰や労働力不足、さらにはデジタル化の進展といった課題が、関係者にさまざまな対応を促しています。このような時代だからこそ、また、京都の伝統的な食文化が持つ知恵が、現代に役立つヒントを提供するでしょう。
京都芸術大学の副学長であり、株式会社オレンジ・アンド・パートナーズの代表でもある小山薫堂が監修する「京都芸術大学 通信教育部 食文化デザインコース」は、2025年から新たな教育モデルをスタートさせます。これにより、食産業が直面する様々な課題に対応するための教育プログラムが展開されます。
新たな学びの形:ハイブリッド型学習
このプログラムでは、基礎理論をオンラインで学び、伝統ある老舗料亭「下鴨茶寮」での体験を通じて実践的なスキルを身に付けることができます。京都の豊かな食文化を体験しながら、現代の食と暮らしに活かすための知恵を探究する機会を提供します。これにより、全国どこからでも自分のペースで学べる環境が整います。
伝統的な場からの多面的な学び
プログラムでは、老舗料亭下鴨茶寮を学びの場として活用し、食文化を支えるさまざまな分野への理解を深めることが可能です。単なる知識の習得を超えて、五感を駆使した実践的な経験に重点を置き、素材選びから料理、そして生産者との関係まで、京都の食文化の全貌を探ります。
受講者は、リアルな問題を解決する能力を養う「問題解決型学習(PBL)」を通じ、未来の食文化に向けた新たな可能性を見つけていくでしょう。
専門家たちとのインタラクション
プログラムでは、料理人、職人、文化人、研究者といった各分野の専門家との対話の機会が設けられます。実践者との直接的な交流を通じて、食を文化芸術として捉える視点を磨いていきます。また、受講者は得た知見を元に自身のプロジェクトを企画し、理論と実践を行き来しながら創造力を育てていくことが求められます。
オンライン学習との相乗効果
この食文化デザインコースの特色である完全オンラインの学びと、実地での体験を組み合わせることで、受講者はより深く理解し、実践的な知識を習得できます。地方に住んでいる方でも、都市部に匹敵する学びの機会にアクセスでき、オンラインで学んだ内容を実際のフィールドで確認できることで、学びが一層充実するのです。
現代に生かす食文化の知恵
本プログラムは、受講者が京都の食文化が育んできた知恵を自らの文脈で再解釈し、日常の生活やビジネス展開、地域活性化に活かすための企画を考える力を育成することを目指します。受講者それぞれの興味や関心に応じて、深く学びを進めることが可能です。
本プログラムを通じて、食を文化芸術として捉える新しい視点を育み、多様な分野との連携を図りながら、食文化の未来を切り拓いていくことが期待されています。
プログラムの詳細
- - 開催時期:2025年度
- - 形式:オンライン講義及び実地研修
- - 対象:食文化デザインコース在学生
- - 内容:講義、実習、対談、フィールドワーク、企画立案など
この新しい取り組みを通じて、受講者一人ひとりが食を通じて新たな価値を創出できる力を育むことが期待されます。これからの食文化を支える人材の育成に向けた一歩が踏み出されるのです。
京都芸術大学 食文化デザインコースの紹介
このコースは、2024年春に開設されたもので、テーマは「食を文化芸術として捉え、おいしい感動をくらしや社会に届ける力を育む」ですす。完全オンラインの形式で、専門家の講義を受講できます。
- - 正式名称:通信教育部芸術学部 文化コンテンツ創造学科 食文化デザインコース
- - 授業料:355,000円(年間)
公式WEBサイト
食文化デザインコース 公式サイト
大学や授業に関するお問い合わせは、以下のアドレスまでお願いいたします。
- - メール:[email protected]
このプログラムを通じて、受講生が新たな価値を見出し、伝統と革新を連結させる学びの場を提供することを目指します。




トピックス(その他)








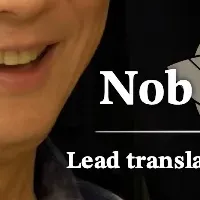
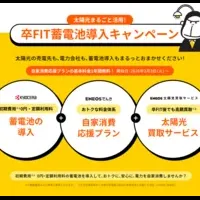
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。