

京都大学が開発した6G向け広帯域伝送装置が車両通信革命を導く
6Gへの進化を促す京都大学の革新技術
近年、通信技術は急速に進化しており、次世代の通信システムである6G(第6世代移動通信システム)への期待が高まっています。この中で、京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授と香田優介助教らによる研究チームは、サブテラヘルツ帯での6G向け広帯域移動伝送試験装置を開発しました。この革新的な技術は、車両のための移動通信インフラ構築の一翼を担うことを目指しています。
800MHz以上の広帯域を実現
京都の研究グループが開発した装置は、サブテラヘルツ帯(100 GHz帯)で、5G標準仕様に準拠しながらも、最大チャネル帯域幅400MHzの2倍以上に当たる920MHzを用いています。この結果、驚異的な伝送レートである1.7 Gbit/sが実現しました。この高速度の通信は、特に交差点などの交通が多い場所での車両認識情報を迅速に伝達することを可能にし、より安全な交通社会の実現へとつながります。
サブテラヘルツの可能性と課題
サブテラヘルツ帯の通信は、その広帯域幅の確保が大きな特徴であり、これにより高精細映像などのデータを無線で高速に伝送することが期待されています。しかし、サブテラヘルツ波は直進性が強く、障害物が多い環境では通信品質が低下するという課題も存在します。今回の研究では、交差点という比較的障害物が少ない環境での通信に着目し、より高精度な車両認識を可能とする試みが行われました。
現在、5Gの普及と技術の進展や需要の高まりとともに、周波数資源の確保が重要な課題となっています。現在使われているSub-6 GHz帯や28GHz帯は、将来的に逼迫する可能性があります。このため、新たな周波数資源としてサブテラヘルツ波の開発が進められています。
未来の交通社会を支える基盤
具体的には、サブテラヘルツ帯での通信を利用して、例えば交差点からの映像情報を迅速に伝送し、交通事故を未然に防ぐためのインフラ整備が期待されています。また、今回の研究成果は、車両向けの移動通信システムを築く上で必要なデータ集積にも寄与します。
新たに開発された伝送試験装置を使った実験から、受信機の構築が適切に行われれば、送信ビームが移動する受信機をピタリと追随しなくても、伝送が行えることが実証されました。これにより、接触しない移動体通信切り替えの可能性も開かれています。
産業界への影響
この技術の進展に伴い、交通の安全性向上や効率化に寄与することが期待されています。具体的には、高速道路や都市部の交通システムがこの超高速無線通信技術を利用することで、大きな変革が起こる可能性があります。サブテラヘルツ波の活用とともに、将来的にはさまざまな分野に大きな影響を及ぼすことでしょう。
詳しい情報や今後の展望については、こちらからご確認ください。
トピックス(その他)


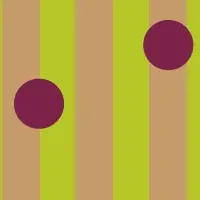
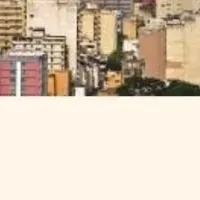






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。