

京都芸術大学が開発したAI学習支援ツールが学生の学びを変える
京都芸術大学が注目のAI学習支援『Neighbuddy』を導入
2024年秋、京都芸術大学にて新たな教育支援プロジェクトが始動します。それは、対話型AI『Neighbuddy』です。このプロジェクトは、学生一人ひとりの学びをより個別最適化することを目的に、京都芸術大学のデジタルキャンパス局(DCB)が独自に開発したものです。学生が授業で取ったノートやバディとの対話を通じて、復習から探究までを支えるこのAIツール。その登場に、学生たちから高い期待が寄せられています。
Neighbuddyとは?
『Neighbuddy』は、学生が書いたノートやその内容に対する対話を基に、個別の回答を提供してくれるAI学習アシスタントです。他のAIと比べても、特に寄り添ってくれる感が強いと学生たちが話すこのツールは、学びを進化させるための可能性を秘めています。特に、学習が苦手な学生にとって、心理的ハードルを下げる方法として効果を発揮することが期待されています。
学生の期待と実績
現在のところ、85.9%の学生が『Neighbuddy』の継続利用を希望しており、その高い比率には驚かされます。さらに、56.2%の学生が「使えなくなると困る」との声を寄せており、110名ほどの協力学生がこのAIを利用して実験を続けています。学生たちの声を聞くと、「ラフに話しかけられるため、気軽に利用できる」という意見や、「自分の考えを客観視できる」といったフィードバックが非常に多く寄せられています。
教員からの評価
このプロジェクトに関わる吉田大作准教授は、Neighbuddyの特性を以下のように述べています。「学生がまずAIに話しかけやすくなる環境を作ることが大切であり、授業中や自学自習の際に、自然に学びを深めていく姿が見られます。」彼の言葉からも、Neighbuddyが教育における新たな可能性を切り拓いていることが伺えます。
今後の展望
Neighbuddyは現在、大規模なパイロット導入が進行中で、さまざまなニーズに応じた改良も行われています。今後は、他の教育機関や研究者とも連携し、さらなる検証を進めていく予定です。利用を希望される方は、京都芸術大学デジタルキャンパス局まで気軽にお問い合わせください。
この新しいAIツールの登場は、学生が自ら学ぶ力を育むための革命的な一歩となることでしょう。特に、学びの孤独を和らげ、支えてくれる存在としての役割が期待されています。AI技術が学生たちの学びをどのように変えていくのか、これからの進展に注目が集まります。
お問い合わせ
このプロジェクトに関わる詳細や、導入に関する質問は以下の連絡先まで。
- - 京都芸術大学 デジタルキャンパス局
- - Email: [email protected]
京都芸術大学は、通学課程と通信教育課程を合わせ、22,000名を超える学生が集まる国内最大規模の芸術大学です。学びの場を通して、社会の中で必要な力を育成し、アートとデザインの力で課題解決に取り組んでいます。公式ウェブサイトもご覧ください: 京都芸術大学


関連リンク
サードペディア百科事典: 京都芸術大学 AI教育 Neighbuddy
トピックス(イベント)


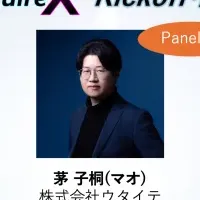




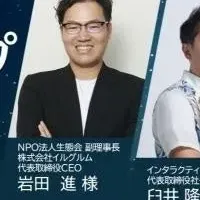

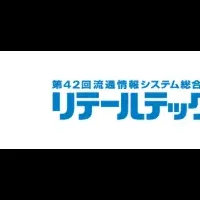
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。