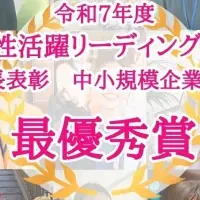

地域住民と共に継承する「粟田祭」の魅力と京都芸術大学の挑戦
地域住民と共に継承する「粟田祭」の魅力と京都芸術大学の挑戦
京都市の東山区に位置する粟田神社では、1000年の歴史を持つ「粟田祭」が行われており、地域住民と京都芸術大学が共同でこの伝統行事を復活させています。古くから悪疫退散を願う神事として親しまれてきたこの祭りは、地元の人々にとって特別な意味を持つイベントです。
本年も、京都芸術大学の学生たちが手がける「粟田大燈呂プロジェクト」によって製作された巨大な灯籠が、特に注目を集めています。参加する学生たちは、巡行時に自らが担ぎ手となり、その力強い姿を披露します。昨年と同様、今年も3基の新たな大燈呂が誕生し、多くの市民や観光客が楽しみにしています。
粟田大燈呂プロジェクトとは?
「粟田大燈呂」は、江戸時代の天正年間に記録が残る伝統行事の一部であり、かつては盛大に行われていましたが一時期途絶えていました。京都芸術大学がこの行事を復活させたのは2008年のこと。以来、学生たちは毎年、粟田地域の文化を理解しながら大燈呂を制作し続けています。
このプロジェクトの一環として、毎年春にはフィールドワークが行われ、地域住民との交流が深められます。そして、本祭りに向けて新たな大燈呂を制作するためのアイデアを募り、それに基づいて作品が完成します。2024年には新たに『奇稲田比賣命』『出世恵美須』『馬』の大燈呂が作られる予定で、学生たちが巡行に参加することで次世代にもその文化を継承します。
今年の開催日とプロジェクトの活動
今年の粟田祭は10月12日に予定されており、その前日には「学内点灯式」が行われます。プロジェクトの公式Xアカウントでは、制作の様子や準備状況が随時更新され、地域の人々や参加者が制作過程を知ることができます。特に8月に行ったワークショップでは、学生たちが島内の子どもたちと共に提灯を制作し、その作品も夜渡り神事で披露される予定です。
この活動は京都芸術大学にとっても重要な試みであり、教育だけでなく、地域社会との関わりを深める力を育む目的があります。約23,000名が在籍する国内最大規模の総合芸術大学として、さまざまな社会実装プロジェクトを展開しています。
地元との協働と未来への展望
京都芸術大学は、地域と大学が手を携え、歴史や文化を次世代に継承するための努力を惜しまない姿勢を見せています。今年の粟田祭もその一環として重要な意味を持ちます。学生たちが作り上げた大燈呂は単なる観光名所ではなく、地域の誇りであり、未来に向けて続いていく伝統なのです。
参加を希望される方は、公式ウェブサイトやSNSを通じて情報を収集し、是非この素晴らしい地域行事に足を運んでみてください。地域の人々と共に、粟田祭の魅力を体感できることでしょう。



トピックス(その他)
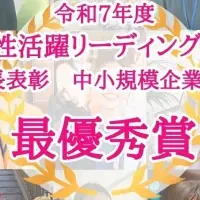
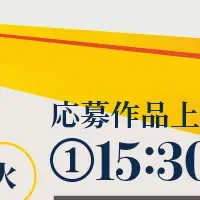




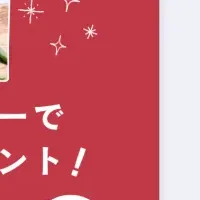
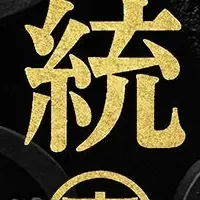

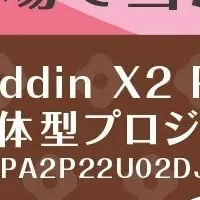
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。