
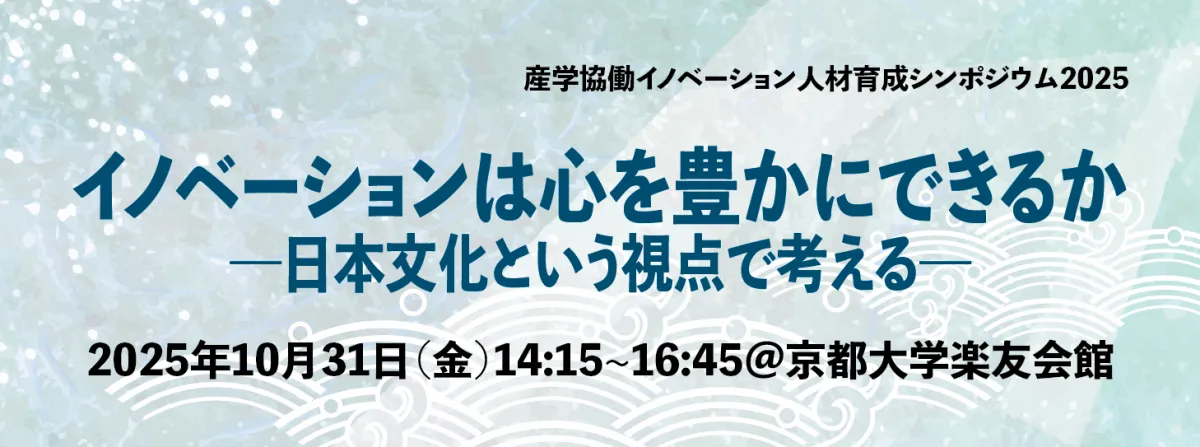
博士人材育成を促進するシンポジウムの成果と意義とは
博士人材育成をテーマにしたシンポジウムの開催
2025年10月31日、京都大学の楽友会館にて、一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会(C-ENGINE)が主催するシンポジウムが行われました。このイベントのテーマは「イノベーションは心を豊かにできるか ― 日本文化という視点から考える ―」で、産学が協力して日本の博士人材育成の新たな形を模索する重要な機会となりました。
開会挨拶とC-ENGINEの意義
シンポジウムの開会に際して、代表理事の國府寛司氏(京都大学理事・副学長)は、C-ENGINEの設立から10年にわたる活動を振り返りながら博士課程学生向けの研究インターンシップの成果を紹介しました。これまでに777件のマッチングを達成し、産学協同によって社会に貢献できる人材を育成していることを強調しました。
来賓として登壇した経済産業省や文部科学省の関係者も、博士人材が企業の基礎研究段階において重要な役割を果たすことの意義を述べ、C-ENGINEの「大学横断型の研究インターンシップ」を評価しました。この取り組みが博士教育と就職問題解決に寄与することが期待されています。
博士学生による実践報告
シンポジウムでは、実際に研究インターンシップに参加した京都大学の疋田純也氏と奈良女子大学の竹内陽香氏が、それぞれの経験を発表しました。疋田氏は、三菱電機でのインターンを通じて「研究力の実践的な手応え」を実感したことを述べ、竹内氏はダイキン工業での数理最適化研究を通じ「探求心と対話力の重要性」を痛感したとの報告がありました。二人の発表からは、異分野に挑むことで得られる多くの学びがあることが伺えました。
基調講演: 文化の溝から生まれる創造性
続いて国際日本文化研究センターの井上章一所長による基調講演が行われました。井上氏は「イノベーションと文化の溝」というテーマで、文化の違いが新たな発想の活力源であると指摘しました。日本における「靴を脱ぐ/脱がない」、食文化における混合といった具体例を交え、異なる文化や価値観との衝突からこそ創造性が織りなされると説きました。これに基づき、文化の境界を越えた新たな視点を持つことが、イノベーションの原点であると結論づけました。
座談会: 文理を越えた創造の促進
シンポジウムの後半では、井上氏と國府氏の間で「イノベーションは心を豊かにできるか」をテーマにした座談会が行われました。この中では、研究インターンシップが異文化・異分野の接点として重要であることが共有され、井上氏は「専門の枠を越え、興味を持つことが創造をもたらす」と述べました。國府氏もまた、C-ENGINEが文化を越えた学びの場であることを強調し、博士学生が広い視野を得ることの重要性を訴えました。
終わりに: 文化と感性を重視したイノベーション
シンポジウムの閉会挨拶では、C-ENGINE理事の古藤悟氏が、技術革新の中で文化や感性、地域性を取り入れることの大切さを再確認しました。デジタル化が進む現代において、見過ごされがちな価値の発見が必要であるとの姿勢を示し、今後も産学協働の取り組みを続けていくことを宣言しました。
C-ENGINEは博士人材の研究力と社会実践力を育むため、今後も研究インターンシップを通じて新たなキャリア形成のモデルを構築していく方針です。これからも異分野・異文化の交じり合いから生まれる創造性を次世代に繋げる取り組みを推進してまいります。
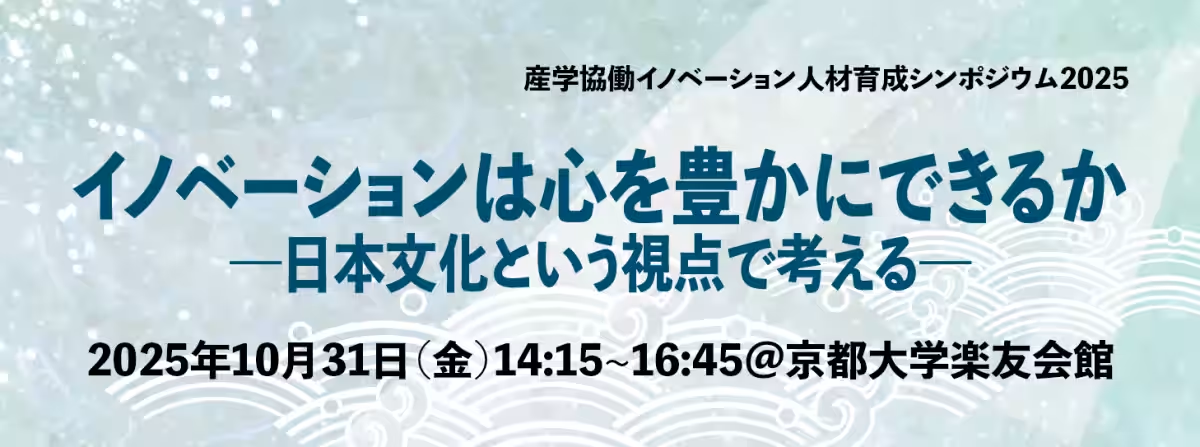
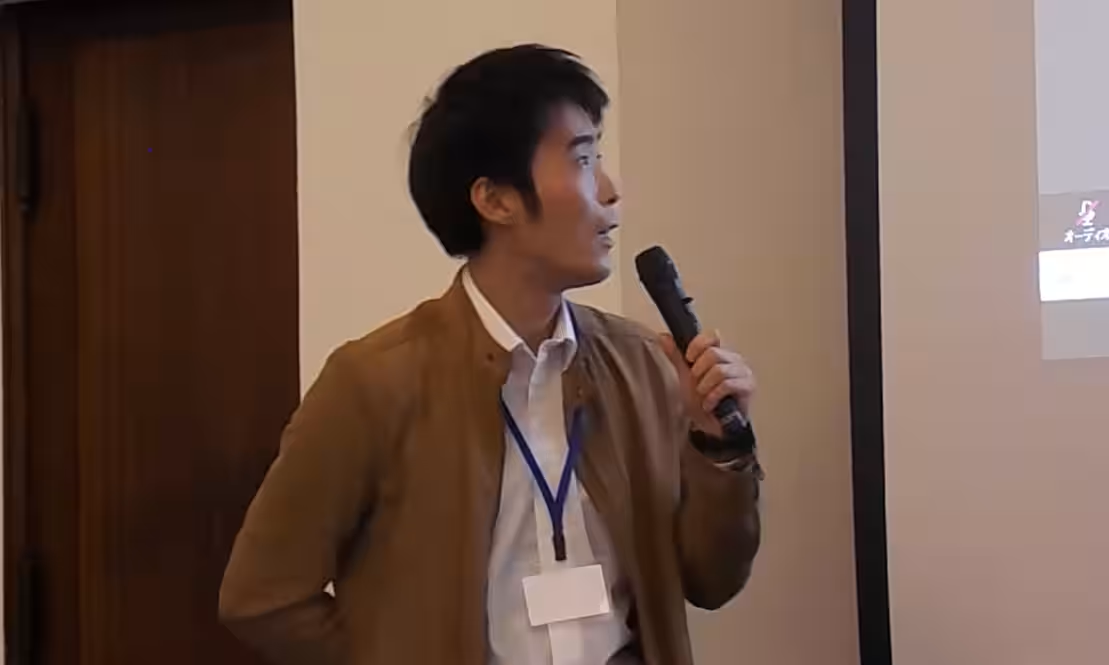






関連リンク
サードペディア百科事典: C-ENGINE 博士人材 研究インターンシップ
トピックス(その他)





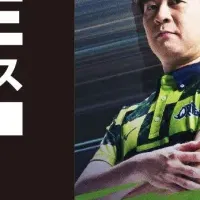


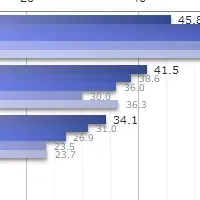
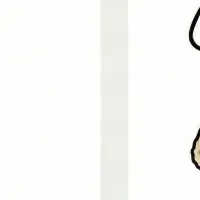
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。