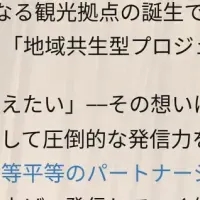

2025年大阪・関西万博で大谷大学が海洋プラスチック問題を語る
2025年大阪・関西万博における大谷大学の取り組み
2025年度、大阪・関西で開催される万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」にて、環境問題に関心が寄せられる中、大谷大学が注目されています。特に海洋プラスチック問題に関する取り組みが、多くの関心を集めています。
2025年9月16日(火)、このイベントの一環として、大谷大学の教授、鈴木寿志氏が「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」というテーマでキーノートセッションを行います。鈴木教授は、その中で年間800万トンにも及ぶ海洋プラスチックが引き起こす被害と、その回収方法の新たな提案を行います。海洋のプラスチックごみの流出は、私たちの生態系への脅威となっています。
環境問題の現状と課題
海洋プラスチックは、生物や漁業だけでなく、それを取り扱う人々にも深刻な影響を及ぼしています。大部分は、焼却や埋立処理されており、持続可能な方法とは言えません。鈴木教授は、特にリサイクルやアップサイクルが進んでいる現状に対して、より効果的な処理方法を模索していく考えを示します。
大谷大学と地域の協働
大谷大学の社会学部、特にコミュニティデザイン学科では、海洋プラスチック問題に立ち向かうため、京丹後市網野町での活動を1999年から実施しています。ここでは、地域の人々や学生との連携をもとに、海浜に漂着したプラスチックの調査および清掃活動に取り組んでいます。これまでの取り組みを通じて得た経験を、万博で広く発表する予定です。
この活動では、海岸に漂着するごみの種類や量を記録し、問題を可視化することで、地域社会の関心を高めることを狙っています。調査データと実績を共有することで、地域住民と学生が協力し、持続可能な社会を築くための意識が広がっていくことを期待しています。
講演の詳細と今後の展望
2025年9月16日のセッションは、時間は13:00から13:40までの予定です。講演内容としては、これまでの活動報告や地域連携の重要性についての発表も含まれています。加えて、学生が開発した「マイクロプラスチック除去装置」などの技術的な側面も紹介し、持続可能な資源循環の方法について議論します。
万博の公式チャンネルでは、このセッションがライブ配信される予定で、広く一般の人々の視聴が可能です。
取材・連絡先
大谷大学広報部は、鈴木教授への個別取材を検討されているメディアの方々へ向けて、連絡を受け付けています。ぜひこの機会に、地域の環境問題に対してどのような解決策があるのか、一緒に考えていきましょう。
大谷大学について
大谷大学は、江戸時代に始まる伝統を持つ教育機関で、自由で開かれた教育を目指しています。近年は、社会のニーズに応える形で、環境問題に対する取り組みを強化しています。これからの社会に必要な人材の育成に貢献するひとつの試みとして、今回の万博への参加が位置付けられています。








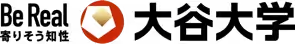
トピックス(旅行)
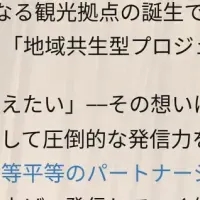




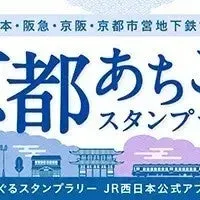


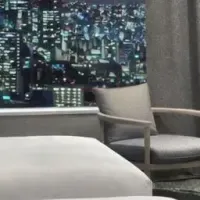

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。